
札幌発の大ブーム「シメパフェ」。仕掛け人が語る、地域文化を育むということ
北海道札幌市
2024.12.26 (Thu)
目次
札幌の新たな食文化として定着した「シメパフェ」。その知名度はいまや全国区となり、札幌旅行の目的にもなるほど。季節を問わず、すすきののシメパフェ専門店にはパフェを求めて長蛇の列ができています。
なぜシメパフェがこんなにもブームになったのか、シメパフェブームの仕掛け人のおひとりであるクリエイティブディレクターの小林仁志さんにお話をうかがいました。
形のないものにどう価値をつけるか

今や、札幌に観光に来て食べない人はいないといってもいいほど、札幌の食文化として深く根付いているシメパフェですが、その歴史は意外と新しく、「シメパフェ」という言葉が登場し始めたのは2016年頃。有限会社アリカデザインの代表でありクリエイティブディレクターの小林仁志さんが、札幌のとあるカフェのブランディングのため、一日を締めくくるパフェを「シメパフェ」と定義づけたのがきっかけでした。
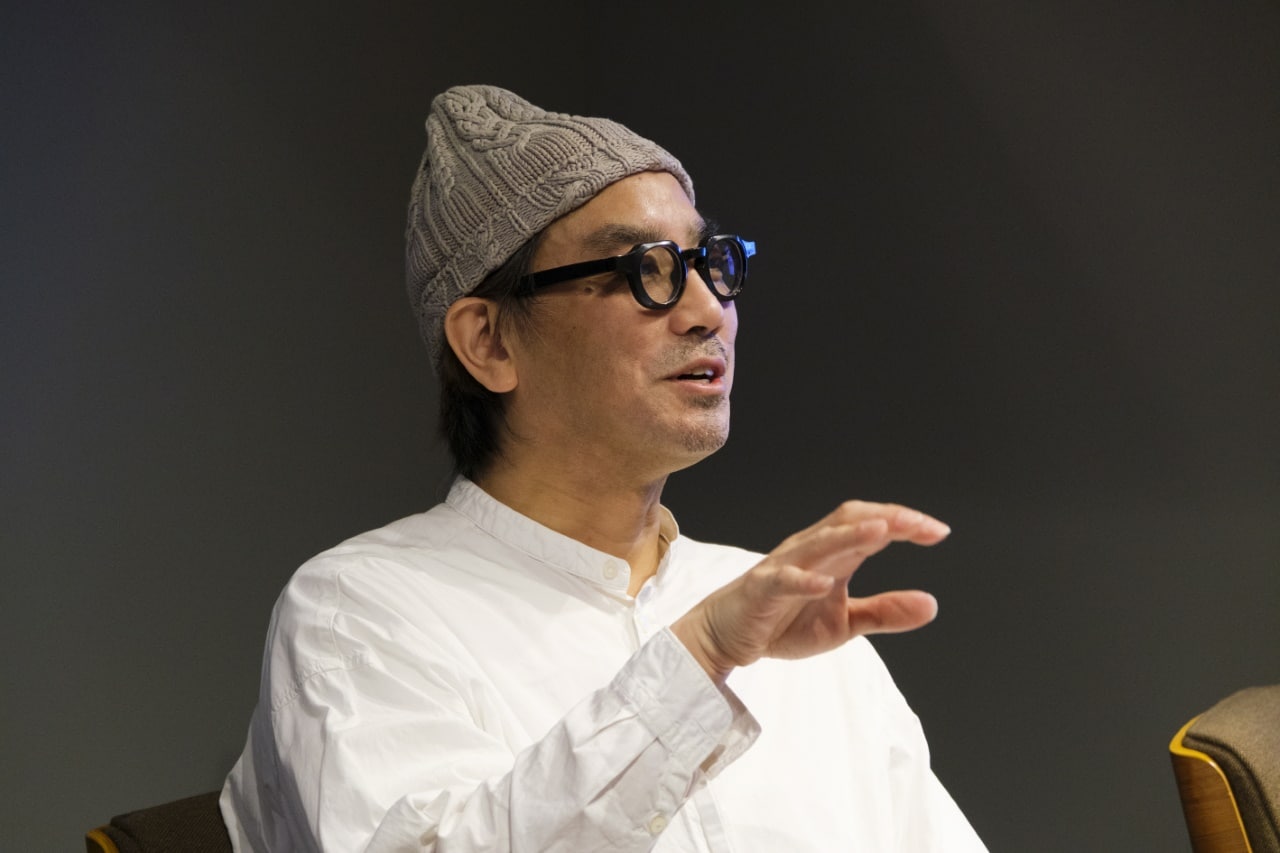
「ブランディングのお仕事は得意分野で、さまざまな商品のブランディングを手掛けていたのですが、シメパフェは、新しい商品をまったく作らずにブランディングするというところからプロジェクトが始まったんです。いわば食体験やライフスタイルのブランディングですね。」
当時の札幌には「シメパフェ」という言葉はありません。「シメパフェ」という言葉を作り、定義づけするところからのスタートでした。この時、ほかのスイーツではなくパフェを選んだことが運命の分かれ目となります。
移住者だからこその着眼点により生まれたシメパフェ
食体験のブランディングをするうえで、数ある食べ物の中からパフェに焦点を絞ったことには、東京出身の小林さんならではの着眼点がありました。
「東京から札幌に移住してきて、札幌には夜にケーキやアイス、パフェなど甘いものを食べるっていう文化があるんだなぁとぼんやりと感じていたんです。」
沖縄にシメステーキの文化があるように、それぞれの地域にシメの文化があるということに着目した小林さん。もともと地域に根付いている文化にシメパフェという名前をつけ、プロモーションしていけば、ひとつの新しい文化が生まれるんじゃないか、という狙いは大的中。それまであまり意識していなかった地元の人たちも、名前をつけられたことで自分たちの文化として改めて認識していったのだそう。

「外から持ってきてメディアが流行らせたものは、すぐに飽きられてしまう。だけど、シメパフェは元々あった文化に名前を付けて拡大しただけなので、なくなることはない。新たに0から作り出して定義づけた名物だったら飽きられるスピードも早かったかもしれないですね。」と、無理やり何か新しいものを流行らせたわけではなかったことが最大のヒットの理由だと語ります。
さらに「スイーツって日々進化していて、フレーバーを増やしたり、サイズを変えたり、アレンジを加えたりはできるが、新しいジャンルを作るのは不可能に近い。パフェというジャンルは、唯一といっていいほど進化していなかったんですよ。」と小林さん。
スイーツとして、まだまだ発展の余地があると感じたこともパフェを選んだ決め手となりました。
「パフェは一口ごとに違う味わいなんです。上の味と下の味は当然違うし、途中に違う食感だったり、違う温度だったり。そこに可能性を感じたんです。」

1店舗だけ『シメパフェ』と謳ったところであまり盛り上がらないということで、地域みんなで盛り上げていこうと賛同するカフェを集めて2015年に「札幌パフェ推進委員会」を設立。「シメパフェ」を札幌の代表する観光資源に育てるべく、小林さんたちの挑戦は始まりました。
食体験として打ち出したことにより、一過性で終わらない地域文化に

連日行列ができる「パフェ、珈琲、酒、佐藤」の店舗。現在、札幌市内で3店舗を展開する
「札幌パフェ推進委員会」を設立後、次々と加盟店が増え、シメパフェは一大ブームに。テレビや雑誌でも大きく取り上げられ、小林さんの読みどおり、札幌の新習慣として知名度を上げていきます。
「これまでカフェをやっていたお店が急にパフェを作り出したり、カラオケ店や焼肉店、寿司店までパフェを出したりするようになったんです。」
市場が大きくなると競争も生まれ、パフェのクオリティや価格もどんどん上昇。一過性のブームではなく、札幌の地域文化として少しずつ地位を確立していったといいます。

小林さんは、グルメとしてではなく、食体験として提案したことが成功の秘訣だったと語ります。
「札幌の観光って食観光だと思っていて、札幌は北海道観光の拠点ではあるけれど、市内に見どころが多いわけではない。そうなってくると食観光がメインになってくる。ジンギスカンや海鮮丼、ラーメンと、札幌のグルメって、ほとんどが主食なんですよね。主食であれば、そのどれかをあきらめなければいけないけれど、その間で食べられるデザート系にはポテンシャルがあるなと思ったんです。」
二軒目にパフェを食べるというライフスタイルは、今や誰もが札幌の文化として認識するようになりました。
ブランディングの経験を活かしてオープンした「パフェ、珈琲、酒、佐藤」

札幌シメパフェ推進委員会を立ち上げ、パフェ熱が高まった小林さんは2016年に自らが運営するシメパフェ専門店「パフェ、珈琲、酒、佐藤」をオープン。
「シメパフェの元祖だとか、先駆けだとかいわれることも多いんですけど、うちの店舗は意外と後発なんです。事務局運営をしながらシメパフェの普及活動をしていく中で、どんどんパフェに興味が出てきて。『自分だったらこうするのにな』とかいろいろ思い始めたタイミングでお店をオープンすることにしたんです。」
「パフェ、珈琲、酒、佐藤」では店名の通り、パフェ、コーヒー、お酒を提供。パフェだけ食べてもいいし、お酒だけ飲んでもいいという、多様化する需要を満たす店作りを意識したといいます。
「みんなでご飯を食べるとなると、1軒目のお店は予約するケースが多いですが、2軒目は予約しない人たちが多いんですよね。そうすると、2軒目は声の大きい人に付いていくっていうパターンがほとんど。でもカラオケや居酒屋だと、楽しめる人が限られる。だから全員が楽しめる2軒目のお店が作りたかったんです。」
2軒目のお店ということを意識して、カラオケボックスに行くのと同じくらいの価格設定にしたのだとか。
「パフェと珈琲を頼んで2000円ちょっと。カラオケと同じくらいの金額で全員が満足できるんだったらいいかなって。」

店がオープンした2016年はちょうどインスタグラムが一気にブレイクした年。
「シメパフェのお店って、薄暗くてある意味落ち着く空間なんだけど、写真を撮ろうとするとあまりきれいに撮れない。だから、うちの店はパフェの輪郭がはっきり映るよう内装を暗くして写真映えを意識して作っているんです。」

2024年4月にリニューアルオープンした「パフェ、珈琲、酒、佐藤」の店舗ではプロジェクションマッピングを楽しみながらパフェが味わえるなど今度は動画映えも意識
「パフェ、珈琲、酒、佐藤」のオープンにより、シメパフェブームはますます加速。札幌シメパフェのお手本的存在として、今もブームを牽引し続けています。
「うちの店作りやパフェを真似していただくのは大歓迎。市場が拡大することはもちろん、そこから競争が生まれて、もっといい商品ができて、もっといい値段で売れる価値が作れれば」と、オープンソースの形を取り、競争を生むことで高いクオリティと価値を維持しているのです。
“もともとあった習慣”文化だからこそまだ伸びる可能性がある

統計的に見ても、シメパフェが札幌の新たな食文化として受け入れられるのは自然な流れだったと話す小林さん。
「ヒットした後に気づいたんですが、北海道はお酒の消費量や、砂糖、チョコレートの消費量が特に高い。あと冬場のアイスクリームの消費量も全国1位なんです。シメパフェブームにより、北海道以外の地域にもどんどんパフェ専門店ができましたが、食文化として根付かないのは元々その土地にシメパフェのような習慣がないからかもしれません。」
シメパフェが流行りのグルメではなく、地域文化となった今、新たな課題も出てきています。
「需要に対して供給が足りていない。いつかはブームが終わるのではないかと怖がって、シメパフェ専門店に振り切れず、中途半端なお店も多い。本気で取り組めるお店がもっと増えてくれば、札幌のシメパフェ文化はもっと盛り上がっていくと思います。」

作って満足ではなく続ける、そして循環させることが文化として根付かせる秘訣だと語る小林さん。
「パフェ、珈琲、酒、佐藤」と姉妹店である「パフェ、珈琲、酒、佐々木」に加え、2021年には大丸札幌店にピスタチオスイーツ専門店「佐藤堂」をオープン。パフェだけに留まらず、創意工夫を凝らしたスイーツを展開しています。これからも小林さんの活躍から目が離せません。
仕掛け人としてだけでなく、当事者、そしてトップランナーとして。まだまだ挑戦は続きます。
パフェ 珈琲、酒、佐藤 / 佐藤堂

住所:北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 8F
公式WEBサイト(外部サイトに移動します。)
https://www.daimaru.co.jp/sapporo/restaurant/post_2.html
パフェ、珈琲、酒、佐藤 本店

住所:札幌市中央区南1条2丁目1番地2 木N I N A R Uビル1・2・3階
公式WEBサイト(外部サイトに移動します。)
http://pf-sato.com/


